あらすじ
孤島のハイテク研究所で、少女時代から完全に隔離された生活を送る天才工学博士・真賀田四季。彼女の部屋からウエンディング・ドレスをまとい両手両足を切断された死体が現れた。偶然、島をN大助教授・犀川創平と女子学生西之園萌絵が、この不可思議な密室殺人に挑む。
感想
このシリーズを読んだことがある人はわかると思うが、所謂森ワールドというものだ。私は、この中で遊ばれている言葉も好きであり、死生観も好きである。単純に、生と死が反している存在であるという話だけではない。死を恐れているわけではなく、死にいたる生を 恐れているといったような新たな感性が触れるこの瞬間がとてつもなくたまらない。その情報を別の表現でも自分の中に落とし込んだ時に、新しいなにかが産まれてくるような気もする。終わることを恐れているのではない。終わりに向かっていく始まった物事を怖がっているように。終わらなければ、怖くないのか。不変であれば、なにも思わないのか。そういった思考が頭の中を巡る間に、生きていることは、病気だという。また、違う言葉に触れたみたい。一種の辞書を開いているようにも思える。この考えが全ての事象を解決できるわけではない。異なる方向性を知る、巡らせる。血が入れ替わっていくかのように、人が入れ替わったように、認知しているか、していないかで、これからの考えの過程が変化するようにも思える。そんな世界観を作り出せるこのワールドの虜になってしまった。実におもしろい。
この作品の中で、強く惹かれた言の葉たち。
“「いいえ、貴女は気がついていないのね。初めて九九を習ったとき、貴女は、7の段が不得意だったはずよ。幼稚園のとき?もっと小さかったかしら?7は特別な数字ですものね。貴女、兄弟がいないでしょう?数字の中で、7だけが孤独なのよ」”
12頁3行目より
“意見を言った端から、すぐ忘れる。こんな内容のない意見を、真面目な顔して、意味のありそうな言葉で包装して発言できるようになったのは最近である。自分の本心を決して口にしないことが、生きていく道なのだ、ということも本能的にではあるが、少しずつわかってきた。調子の悪い車を騙し騙し走らせるようなものだ。目的地に着きさえすれば、それで良い。”
25頁15行目より
“「大丈夫です。先生こそ……、お疲れでしょう?」萌絵は脚を組んで言った。
「そうね、マカデミアナッツよりは、ちょっとましかな…」
犀川は真面目な顔をして言った。少し考えてから萌絵が言う。
「マカデミアナッツ?どういう意味ですか?」
「はは、意味はないよ」犀川は笑う。
「意味のないジョークが最高なんだ」”
184頁12行目より
“「思い出と記憶って、どこが違うか知っている?」犀川は煙草を消しながら言った。
「思い出とは良いことばかり、記憶は嫌なことばかりだわ」
「そんなことはないよ。嫌な思いでも、楽しい記憶もある」
「じゃあ、何です?」
「思い出は全部記憶しているけどね、記憶は思い出せないんだ」”
289頁1行目より
“「私は、先生と近くでお話ししている方が楽しいわ」
「何故?」犀川がすぐにきいた。彼はメールを半分ほど読んだところだった。
「それは、君の習慣が、そういう感情を君に与えているからだろうね。生まれながらにして、電子空間でコミュ二ケーションをしていれば、そうは感じないだろう、きっとね…。 それに、今に、電子空間で手も握れるようになる。肉体的な感触のレスポンスが欲しいというのは、人間の贅沢な欲求だけど、多少のエネルギィの無駄使いで解決する。やはり小言な問題だ」
「私はそうは思いません」
「それは、君の意見。僕は自分の意見を押しつける気はないよ」犀川は振り向いて言った。 「君の意見の方が今はメジャだということも認めるよ。ほとんどの人間は、自分の生きてきた時代を遡って、過去の歴史的な習慣にも縛られるものだ。それを非難するつもりはない。人間ほど歴史を後生大事にする生き物はいない」”
365頁10行目より
“「先生…、現実って何でしょう?」萌絵は小さな顔を少し傾けて言った。
「現実とは何か、と考える瞬間にだけ、人間の思考に現れる幻想だ」犀川はすぐに答えた。 「普段はそんなものは存在しない」
「でも、現実と夢とは明らかに違うでしょう?」
「他人の干渉を受ける、あるいは他人と共有している、という意味で現実はやや自己から独立したものとして自覚されているね」 犀川はカップをもちあげながら言う。コーヒーはもう冷めていた。
「でも、他人に干渉を受けない、あるいは他人と共有しない現実も、一部分だが努力すれば構築することができるだろう?たとえば、未来には、必ず個人の現実はそういった方向へ向かうはずだ。何故なら、みんながそれを望んでいる。だから…、現実は限りなく夢に近づくだろう」”
357頁13行目より
“時計の文字盤には、本当に不思議なことがある。一般に文字盤には、1から12までの数字が書かれている。これは当たり前だ。ところが、一時間は六十分なのである。何故、1から60までの数字を書かないのか。「2のところに長針があったら10分です」と小学生に先生は本気で教えている。子供には、世間の厳しさを教えるのだろうか、と犀川は思う。その不合理さに、どうして誰も気がつかないのか。こんな不親切な文字盤のメータが他にあるか、周りを見回してみると良い。一番良い解決方法は、五分を一分にすることだろう。一時間を十二分にすれば良いのである。”
367頁5行目より
“「日本では、遊ぶとき、混ぜてくれって言いますよね」犀川は突然話し出した。
「混ぜるという動詞は、英語ではミックスです。これは、もともと液体を一緒にするときの言葉です。外国、特に欧米では、人間は仲間に入れてほしいとき、ジョインするんです。混ざるのではなくて、つながるだけ…。つまり、日本は、液体の社会で、欧米は固体の社会なんですよ。日本人って、個人がリキッドなのです。流動的で、渾然一体になりたいという欲求を社会本能的に持っている。欧米では、個人はソリッドだから、決して混ざりません。どんなに集まっても、必ずパーツとして独立している……。ちょうど、土壁の日本建築と、煉瓦の西洋建築のようです」”
430頁4行目より
“「16進法だよ。西之園くん」犀川は答える。
「レッドマジックのプログラムの中で、数字をカウントしている変数は、インティジャ、つまり整数型だった。コンピュータは、数字を2進法で扱うけど、プログラマはそれを四桁ずつまとめて、16進法で表記するんだ。普通の整数の場合、2バイトといってね……、16新法で四桁、つまり、16の4乗までの数が使えることになる」”
465頁7行目より
“「死を恐れている人はいません。死にいたる生を恐れているのよ」四季は言う。
「苦しまないで死ねるのなら、誰も死を恐れないでしょう?」”
495頁4行目より
“「ニキビのようなもの…。病気なのです。生きていることは、それ自体が、病気なのです。病気が治ったときに、生命も消えるのです。そう、たとえばね、先生。眠りたいって思うでしょう?眠ることの心地よさって不思議です。何故、私たちの意識は、意識を失うことを望むのでしょう?意識がなくなることが、正常だからではないですか?眠っているのを起こされるのって不快ではありませんか?覚醒は本能的に不快なものです。誕生だって、同じこと……。生まれてくる赤ちゃんって、だから、みんな泣いているのですね。生まれたくなかったって……」 ”
495頁13行目より
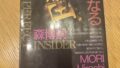



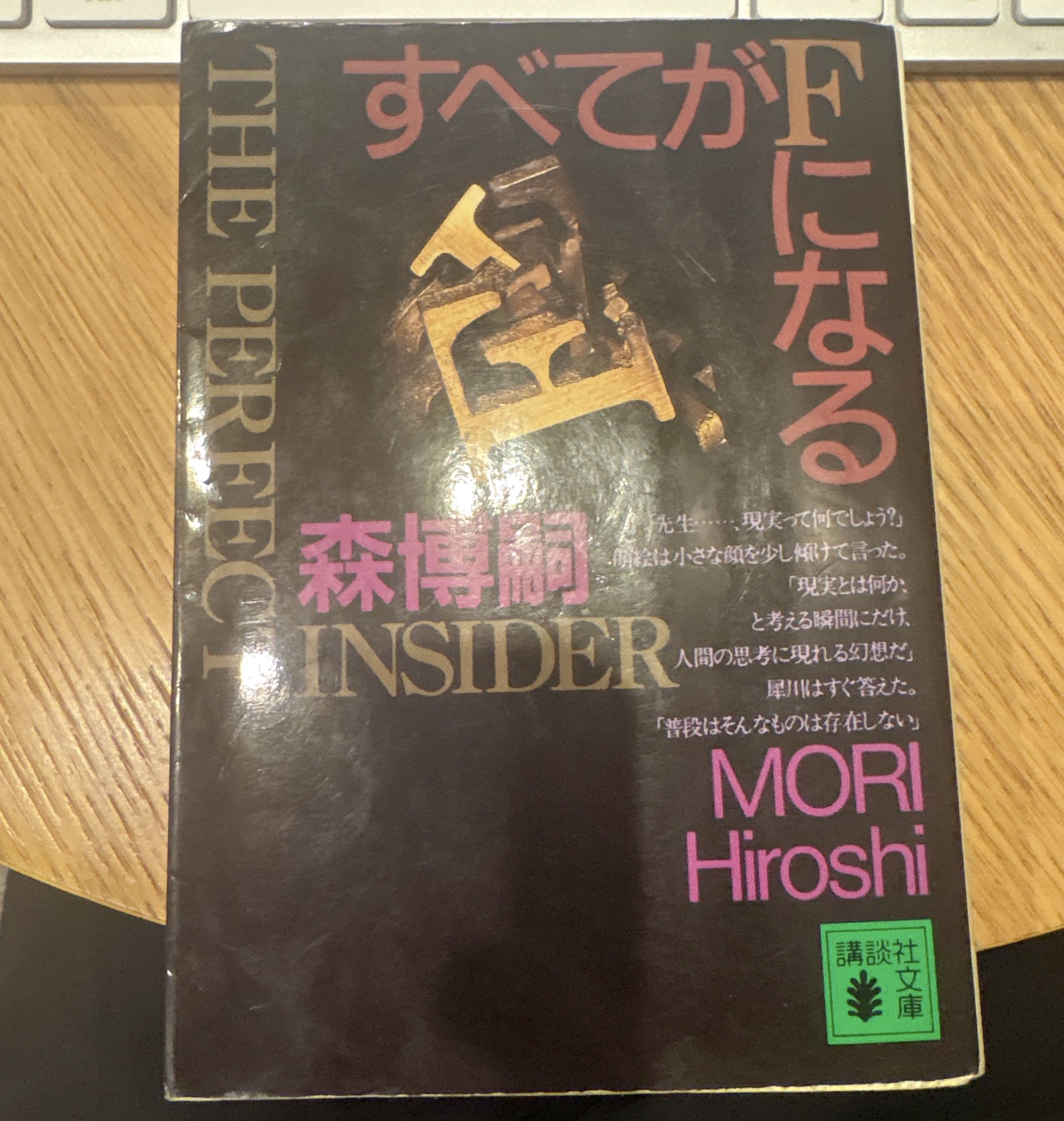
コメント